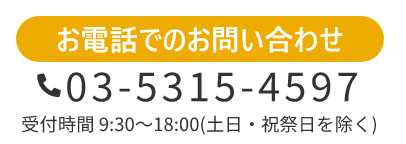【クリニック経営者必見】再生医療の第一種・第二種・第三種の違いと導入時の注意点|行政手続きのプロに依頼すべき理由とは?
クリニック開業・経営



この記事の監修
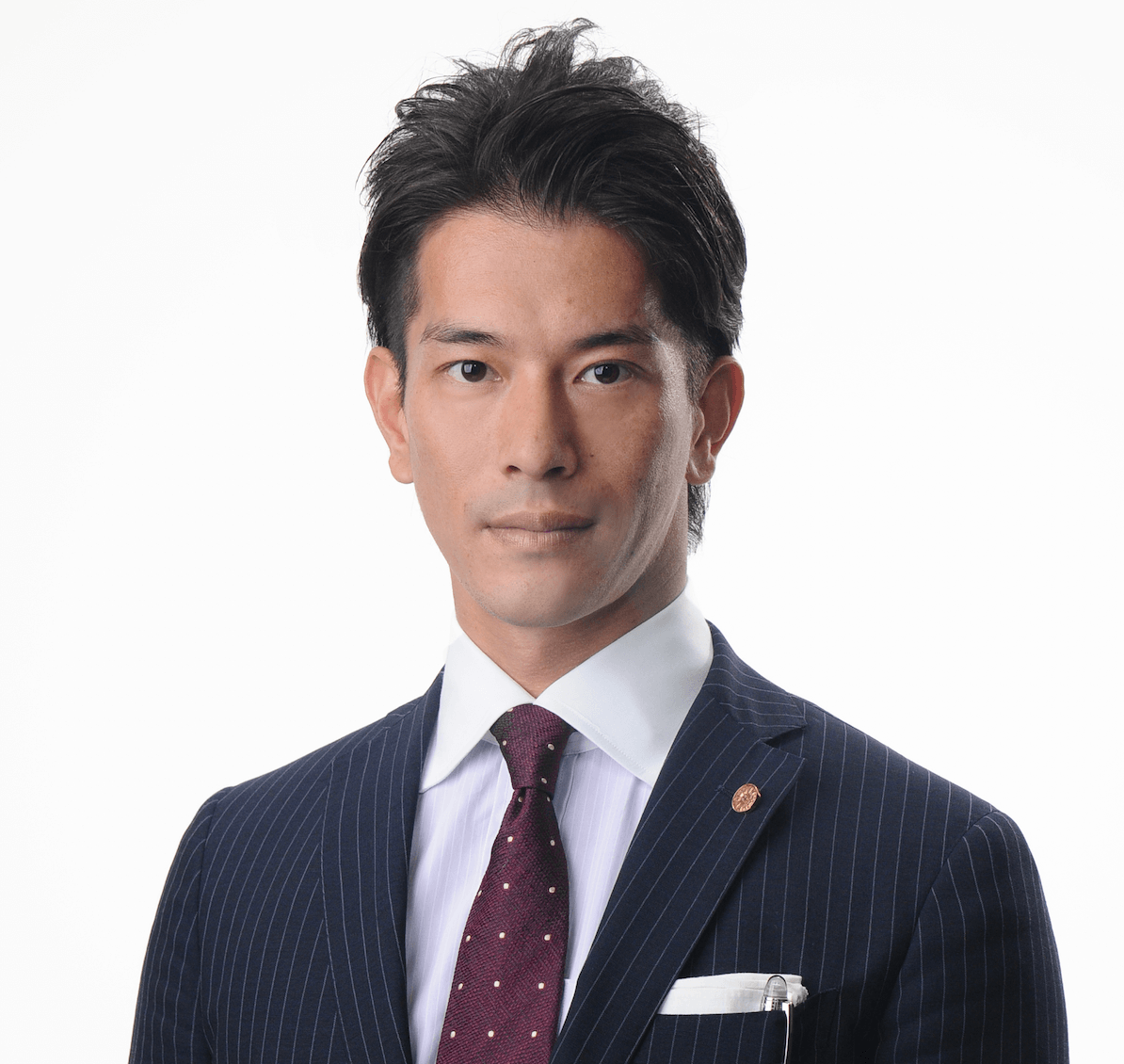
行政書士法人RCJ法務総研 代表 / 行政書士
株式会社リアルコンテンツジャパン(経済産業省認定経営革新等支援機関) 代表取締役
古川 晃
医療許認可の専門家として17年、医療法人設立・分院開設・合併・解散・一般社団法人による診療所開設など医療許認可1500件以上 クリニック様の助成金・補助金・融資などの資金調達100億円以上の支援実績
近年、幹細胞治療やPRP療法といった再生医療は、美容や整形外科、婦人科など幅広い分野で注目を集めています。
しかし、再生医療の提供には非常に厳格な法規制が存在し、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療安全確保法)」に基づく手続きや許認可の取得が不可欠です。
この記事では、クリニック経営者の方々が理解しておくべき再生医療の第一種・第二種・第三種の違いを解説し、許可・届出手続きの流れや行政書士の活用の重要性をわかりやすく紹介します。
再生医療の導入を検討されている方は、最後までお読みください。
再生医療とは?医療法人・自由診療クリニックが注目する理由
「再生医療」とは、体の細胞や組織の機能を回復・再生させる医療技術の総称であり、以下のような先進的な治療法が含まれます。
- PRP療法(多血小板血漿療法)
- 幹細胞治療(脂肪由来幹細胞など)
- 免疫細胞療法
- ES細胞・iPS細胞を用いた治療
これらは保険適用外の自由診療で提供されることが多く、高単価でありながらリピーターが見込める点から、経営戦略上大きなメリットがあります。
第一種・第二種・第三種再生医療とは?分類ごとの違いを解説
第一種再生医療:高度リスクを伴う治療
特徴:
- iPS細胞・ES細胞などを用いた治療
- がんや重度の脳疾患、再生不可能とされていた組織の再構築などに用いられる
- 大学病院や特定機関以外では現状ほとんど実施不可
クリニック経営者にとっての関係性:
- 実務上取り扱うことは少ない
- ただし、共同研究などで関与する場合は極めて高度な申請が必要
第二種再生医療:中程度のリスク、脂肪由来幹細胞など
特徴:
- 自家細胞を用いた幹細胞治療(自己脂肪、自己骨髄など)
- 特定細胞加工物の製造委託などが関係
- がん免疫療法や慢性疼痛に対する細胞治療などが含まれる
必要な手続き:
- 提供計画の届出
- 特定認定再生医療等委員会による審査
- 厚生労働省への提出と公開
対象クリニック:
- 自由診療型の美容クリニック
- 整形外科クリニック
- 予防医療を行うクリニック
第三種再生医療:比較的安全性が高い治療法
特徴:
- **PRP療法(多血小板血漿療法)**など、血液を使った治療が代表例
- 安全性が高く、リスクは軽度
- 審査機関も認定再生医療等委員会(特定ではない)
必要な手続き:
- 提供計画の届出
- 再生医療等委員会の意見取得
- 厚生労働省への届出
対象クリニック:
- 美容外科・整形外科
- 婦人科(不妊治療やアンチエイジングなど)
- スポーツクリニック(怪我の治療)
再生医療を導入する際の主な行政手続きと流れ
- 治療内容の分類確認(第一種〜第三種)
- 認定再生医療等委員会または特定認定委員会の選定
- 提供計画書・説明文書・同意書などの作成
- 委員会審査・意見取得
- 厚生労働省への提供計画届出(年1回報告義務あり)
- 実施後のモニタリング・報告体制の整備
この手続きは極めて煩雑であり、医師一人では対応しきれないことが多いため、外部の専門家と連携することが重要です。
クリニックが医療専門の行政書士を活用すべき3つの理由
法律上、行政手続の代行ができるのは行政書士ということになりますが、行政書士もそれぞれ専門分野が異なります。
特に医療は専門性が高く、経験豊富で詳しい行政書士は全国でも限られています。
① 提供計画書の作成と添付書類の精度が問われる
再生医療等提供計画の届出には、技術的根拠・リスク評価・患者への説明内容を網羅した計画書の作成が必要です。
医療専門の行政書士は、過去の実例や審査通過事例を踏まえた適切な文書作成が可能です。
② 審査機関(委員会)との調整がスムーズになる
認定委員会への申請時には、形式不備や情報不足による差し戻しが頻発します。
医療専門の行政書士が入ることで、委員会とのやり取りが円滑になり、許可取得までの期間短縮にも繋がります。
③ 法改正や最新の行政指導に対応できる
再生医療関連の規制は頻繁に改正されており、旧情報のまま進めると申請が通らないリスクがあります。
医療専門の行政書士は常に最新の動向を把握しているため、安全かつ確実に導入できます。
導入時に専門家を使わなかったクリニックの失敗例
以下は、実際に再生医療導入で失敗したクリニックの一例です。
- PRP療法を開始したが、計画届出をせずに厚労省の指導対象に
- 委員会の選定ミスにより半年以上申請が止まった
- 文書不備により届出受理が拒否され、広告も打てなかった
これらは、専門家による事前チェックや申請代行があれば回避できたケースです。
再生医療導入を成功させるために今すぐ始めるべきこと
- 第一に、どの種に該当するかを明確にする
- 第二に、委員会と厚労省への手続きを正しく設計する
- 第三に、医療専門の行政書士などの専門家を早期に巻き込む
とくに再生医療は、治療開始後に不備が見つかれば即時中止となるリスクもあります。
まとめ|再生医療導入は行政書士とのタッグで確実に
再生医療の導入は、クリニックにとって自由診療の収益向上を狙える大きなチャンスです。
しかし、制度上の複雑さや厳格な届出・審査制度があるため、専門知識のある行政書士との連携が不可欠です。
もし再生医療の導入をご検討中であれば、再生医療に精通した行政書士へ一度ご相談ください。
【再生医療導入のご相談はこちらから】
✅ 再生医療等提供計画の届出サポート
✅ PRP療法・幹細胞治療の法令対応支援
✅ 審査委員会選定・文書作成・届出代行すべてお任せ
▶ ご相談・お問い合わせは【リアルコンテンツジャパン】まで

医療法人の設立・運営面についてサポートします!
医療許認可の専門家として17年。医療許認可1,500件以上の実績。
医療法人化または一般社団法人による診療所開設、
分院開設、医療法務顧問、補助金、助成金支援までサポートしております。
医療法人の専門家にお気軽にご相談ください