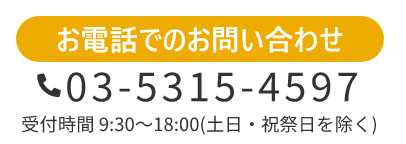保険医療機関の新規指導・集団指導・個別指導とは?クリニック経営者が知っておくべき重要ポイントと対策
クリニック開業・経営



この記事の監修
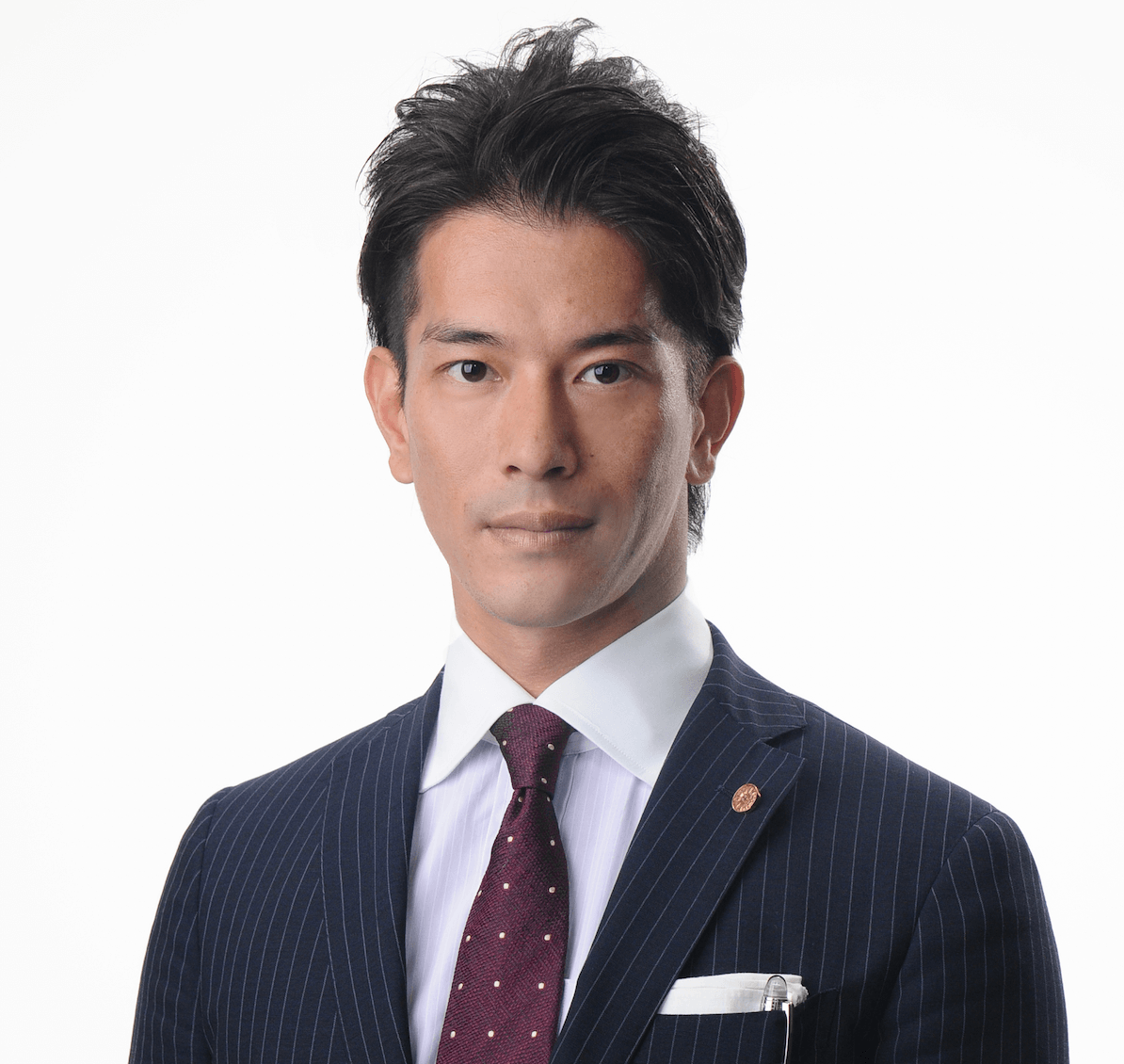
行政書士法人RCJ法務総研 代表 / 行政書士
株式会社リアルコンテンツジャパン(経済産業省認定経営革新等支援機関) 代表取締役
古川 晃
医療許認可の専門家として17年、医療法人設立・分院開設・合併・解散・一般社団法人による診療所開設など医療許認可1500件以上 クリニック様の助成金・補助金・融資などの資金調達100億円以上の支援実績
クリニックを開業し、保険診療を行うには「保険医療機関」としての指定を受ける必要があります。
しかし、これで終わりではありません。
開業後、一定の時期が来ると必ず受けることになるのが「新規指導」。そして経過観察や問題の有無に応じて「集団指導」「個別指導」へと進む可能性があります。
これらの「指導」は、保険診療を続けていく上で避けては通れないプロセスであり、場合によってはクリニックの経営に大きなダメージを与えることもあります。
この記事では、保険医療機関に課される3つの指導の概要とそれぞれの違い、クリニック経営者が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
1. 保険医療機関の指導とは?
保険医療機関としての指定を受けたクリニックには、診療報酬の適正な請求と医療の質の維持が求められます。
そのチェック体制の一環として、厚生局などの保険者によって行われるのが「指導」です。
指導の主な目的は以下の通りです。
- 不正請求の防止
- 診療内容と請求の整合性確認
- 医療の質の確保
- 医療費の適正化
つまり、保険診療を行う以上は、これらのルールを順守しているか、定期的に第三者によるチェックが入るということです。
2. 新規指導とは?必ず受ける初回チェック
対象とタイミング
新規に保険医療機関として指定されたクリニックは、原則として1年以内に「新規指導」を受けることになります。
対象は新規の保険医療機関すべてであり、逃れることはできません。
ただし、時期については地域によってで、すぐ来ることもあれば、数年来ないという地域もあって、ある日突然来ることもあります。
内容と流れ
- 事前に提出された診療録やレセプトを元に審査
- 管轄の厚生局または地方厚生局事務所で面談
- 指導医や査察官からの質問に答える形式
よくある質問例
- 「診療録の記載が不十分ではありませんか?」
- 「投薬日数が長すぎる傾向がありますが?」
- 「請求と実際の診療内容に乖離がありますが?」
適切な準備と書類整備がなされていないと、悪印象を与え、以後の指導リスクが高まります。
3. 集団指導とは?経過観察的なフォローアップ
新規指導後、特に重大な問題がなければ、次の段階として「集団指導」が行われます。
これは、類似ケースの医療機関を複数集めて、共通の注意点を説明する研修形式の指導です。
開催内容
- 医療法令の遵守についての講義
- 診療報酬制度の解説
- 不適切事例の共有と改善指導
ポイント
- 質疑応答は少なめ
- 個別の指摘は行われない
- ただし、ここでの注意点を無視すると、個別指導へ移行する可能性あり
4. 個別指導とは?経営に影響を与える要注意フェーズ
最も避けたい「個別指導」
個別指導は、実地調査を含む徹底的な精査が行われる、最も厳しい指導の一つです。
主に以下のような理由で通知されます。
- レセプトの記載に疑義がある
- 投薬、処置、検査等で不適切な傾向がある
- 患者や同業者からの苦情・通報
- 集団指導後の改善が見られない
- 近傍、類似の診療所と比較して著しく平均保険点数が高いことが目立つ など
具体的な流れ
- 事前通知により資料提出を求められる
- 当日、担当官が直接訪問または呼び出し
- 詳細なレセプト分析・診療録チェック
- 医師本人への事情聴取
- 最終的な是正措置の指導・指摘
ここで重大な違反が見つかると、返還請求、保険医療機関指定の取消、医業停止処分といった重大な行政処分につながる恐れがあります。
5. 指導を受ける前に準備すべき書類と体制
以下のような資料は日頃から整備しておくことが重要です。
- 診療録(SOAP方式で記載)
- 処方履歴・投薬理由の記録
- 各種検査の必要性・根拠の記録
- レセプトとの整合性チェック体制
- 職員教育記録(法令遵守に関する)
6. 医療に詳しい行政書士との連携が指導対策において必須である理由
行政書士ができるサポートとは?
- 書類作成や整備指導(診療録や備品台帳など)
- 指導通知が来た際の初期対応アドバイス
- レセプト審査の疑義対応サポート
- 不備があった場合の改善報告書の作成支援
- 行政との対応時における法的アドバイス
- 行政処分に対しての不服申し立て 等
ただし、すでに実際に不正があったものをなんとかごまかし隠し通すということはできません。
専門家を置かず自己判断で対応した場合のリスク
- 記録不足による行政指導
- 記載ミスが累積し、返還請求のリスク拡大
- 是正報告が適切でなく再指導対象に
- 保険指定取り消しのリスク
7. よくある失敗事例と実例
| ケース | 内容 | 結果 |
| Aクリニック | 定型的な診療内容のコピー記載 | 厳重注意+再指導 |
| Bクリニック | レセプトと実態に不一致 | 請求額返還 |
| Cクリニック | 個別指導時の不適切対応 | 保険医登録取り消し |
これらのケースはいずれも「専門家のサポートを受け、事前対策や改善ができていれば回避できた」と考えられるものです。
8. 詳しい行政書士に相談すべきタイミングとメリット
- 開業前〜指定申請時:新規指導に備えた準備
- 開業後1年以内:書類整備と模擬指導対策
- 指導通知を受けた時点:即時対応とリスク分析
- 指導後:改善報告と再発防止策の立案
早期に行政書士と連携することで、“経営ダメージの最小化”と”保険診療継続の安定化”が可能になります。
9. まとめ:指導対応は経営戦略の一部と捉えるべき
保険医療機関として健全に経営を継続するためには、「指導」を単なる監査ではなく、診療体制を整えるきっかけととらえる視点が必要です。
返還や指定取り消しは致命的な打撃となります。
そして、複雑な法令・手続き・記録対応には、医療法務を熟知した行政書士の存在が欠かせません。
【最後に】指導通知が届いたら、まず行政書士へ相談を
保険診療の継続がクリニック経営の基盤となる以上、「指導」への適切な対応は生命線とも言えます。
万が一、通知を受けた際には、慌てて自己対応せず、まずは専門の行政書士へご相談ください。

医療法人の設立・運営面についてサポートします!
医療許認可の専門家として17年。医療許認可1,500件以上の実績。
医療法人化または一般社団法人による診療所開設、
分院開設、医療法務顧問、補助金、助成金支援までサポートしております。
医療法人の専門家にお気軽にご相談ください