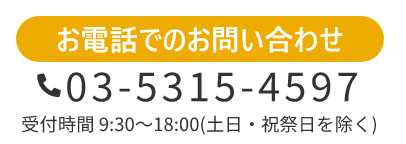一般社団法人による診療所開設の実務ガイド|一般社団法人スキームでのクリニック開業に必要な手続きと注意点
一般社団法人による診療所開設


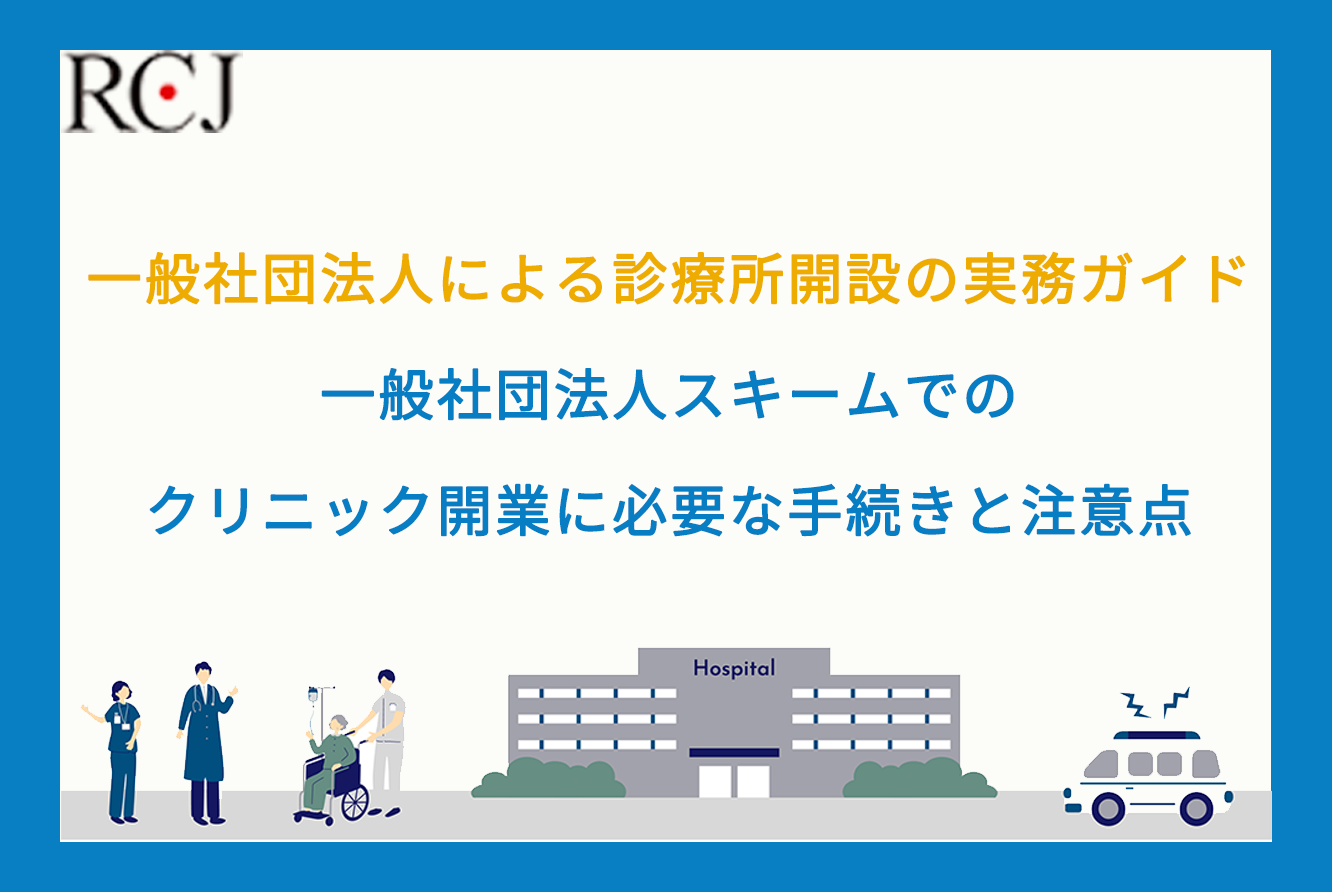
この記事の監修
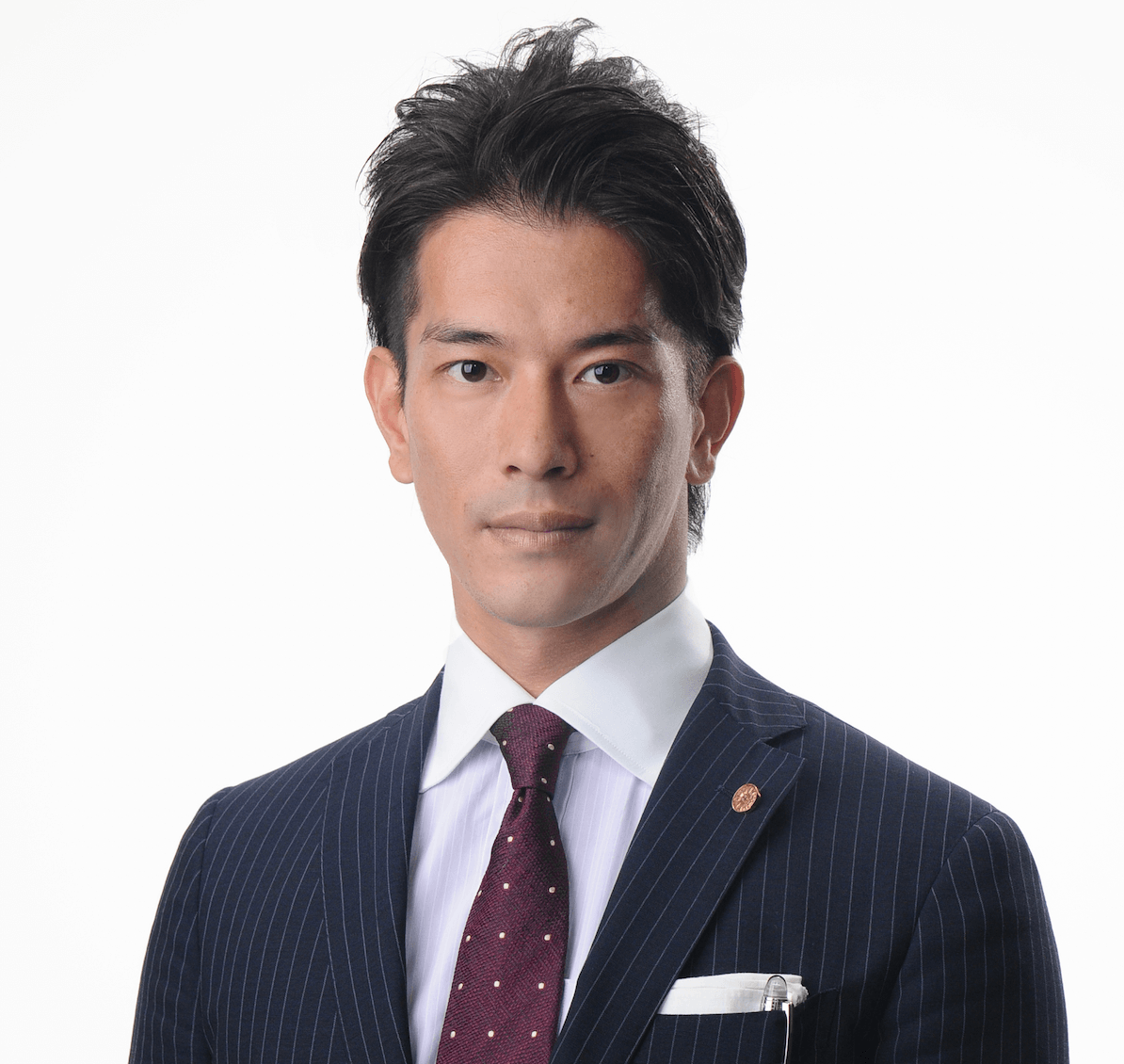
行政書士法人RCJ法務総研 代表 / 行政書士
株式会社リアルコンテンツジャパン(経済産業省認定経営革新等支援機関) 代表取締役
古川 晃
医療許認可の専門家として17年、医療法人設立・分院開設・合併・解散・一般社団法人による診療所開設など医療許認可1500件以上 クリニック様の助成金・補助金・融資などの資金調達100億円以上の支援実績
近年、「非営利型一般社団法人による診療所開設」というスキームに注目が集まっています。
従来、医師個人や医療法人による開業が一般的でしたが、様々な観点から、非営利型の一般社団法人を活用した開業形態が関心を集め、全国でもかなり浸透してきました。
特に以下のような方々にとって、このスキームは有効です。
- 医療法人ではできない事業を行いたい人
- 他店舗展開を目指しているクリニック経営者
- 再生医療や自由診療領域での新規展開を狙っている経営者
本記事では、「一般社団法人による診療所開設」に関する基本知識から、開設に必要な行政手続き、許認可の注意点、そして医療専門の行政書士をパートナーにすべき理由について詳しく解説します。
一般社団法人とは?医療法人との違い
一般社団法人の基本構造
- 非営利を徹底した定款である必要がある
- 法人の設立自体は定款認証と設立登記のみでできるが、診療所の開設は別途許可が必要
- 出資の概念がなく、社員(構成員)が議決権を持ち構成される(株や持分はない)
- 社員は最低2名、理事は最低3名、そのうち1名を代表理事とする
- 非営利であるため、医療法人と同様に、配当は不可。配当に類似する行為も不可。
医療法人との比較
| 項目 | 一般社団法人 | 医療法人 |
| 配当 | 不可 | 不可 |
| 設立ハードル | 設立自体は容易(登記のみ)。ただし診療所開設には許可が必要 | 原則個人開設の実績が必要。都道府県の認可 |
| 診療所開設の可否 | 原則不可(例外あり) | 可 |
| ガバナンス | 自由度が高い | 制約が多い |
一般社団法人でも診療所を開設できるのか?
原則:診療所の開設主体は「医師・歯科医師個人」または「医療法人」であった
かつては、原則として診療所の開設者は以下のいずれかに限定されていました。
- 医師個人または歯科医師個人による開設
- 個人開設の実績を積んでから医療法人設立認可
- 医療法人の診療所(分院等)として開設認可
例外的に開設できるケースとは?
一般社団法人であっても、非営利を徹底している非営利型の一般社団法人であって保健所による開設許可を得られれば、一般社団法人を経営主体とした診療所運営が可能になります。
ただし、保健所は基本的にこの許可を出したがらず、医療法人での開設進めてきたり、なにかと理由をつけては書類を受け取らず、審査を開始しないという地域もあります。
また、人員の関係で手が足りず、非常に審査に時間がかかることもあったり、やりたくないがために「医療法人にせよ」の一点張りで放置されるケースも多くあります。
そのため、相当程度制度を熟知し、行政との折衝能力が高い経験豊かな行政書士でないとなかなか許可にたどり着けないことが多いです。
診療所開設に必要な許認可と行政手続き
開設許可
診療所の開設許可を得るには、「非営利性」と「永続性」の疎明が必須です。
- 剰余金の配当や配当に類似した行為を一切しないこと(非営利性)
- 営利法人(民間企業)などが経営に関与し、実質的に経営を支配していないこと。営利法人は診療所の経営はできず、一般社団法人を隠れ蓑に実質的に営利法人が経営をしているような状況は医療法違反(非営利性)
- 事業計画、予算書及び預金残高証明などから、安定した経営を行い、潰れることがないことを疎明すること(永続性)
- 各種コンプライアンスを遵守し、適法に経営ができるガバナンスが整っていること(永続性)
これらを疏明できなければ許可は得られません。
この審査にかかる時間は保健所ごとに異なり、早い保健所で3ヶ月程度、遅いところは1年以上かかっているケースもあります。
それどころか、そもそも話を聞いてもらえない、受け取ってもらえない、というような、門前払いのような仕打ちで諦めさせようとしてくることもあります。
しっかりと専門家と相談の上準備をしていきましょう。
一般社団法人スキームのメリットとリスク
メリット
- 非医師も代表理事になれる(保健所によっては嫌がられる)
- 本来業務・附帯業務・附随業務に限定されない
- 都道府県の認可がない
- 医療法人より自由度は高い(ただし非営利性は徹底)
リスク・注意点
- 名義貸しの疑いを持たれるリスク
- 営利法人の関与、支配を疑われるリスク
- 誤ったスキームで開設しようとすれば不許可や許可の取り消しもあり得る
- そもそも許可がおりない
- 工数がかなりかかる
- 許可にものすごく時間がかかる場合もある
- 支援できる専門家が少ない(専門性が著しく高い)
行政書士が果たす重要な役割
なぜ専門の行政書士が必要か?
医療機関は人の生命に関わる重要な存在であり、営利目的で経営をすることはできず、規制が厳格です。
仮になんとか許可を得られたとしても、法律に反すれば開設後に許可の取り消しもあり得ます。
この分野の経験豊富な行政書士であれば:
- 保健所との事前協議の代行
- 開設届や関連書類の作成代行
- 医療法人スキームとの比較提案
- スムーズな許可取得
法的に根拠と経験に基づき、開設までのあらゆるリスクを回避し、円滑な事業スタートを支援することができます。
ただし、支援できる専門家は全国でも人数は限られています。
一般社団法人スキームを活用する際の実務ステップ
ステップ1:非営利型の一般社団法人の設立
非営利性を徹底する定款でなくてはならず、人的要件も満たしている必要がある。
- 最低社員2名
- 最低理事3名のうち1名を代表理事
- 理事の総数のうち三親等以内親族の割合が⅓を超えないこと
等、専門家と協議しながら進めていくこと。
ステップ2:保健所との事前協議
開設予定地を管轄する保健所と必ず事前相談を行い、各種問題がないか確認し調整をしていくことが不可欠。
ここに時間と工数がかかり、早い保健所で3ヶ月程度、長ければ1年以上かかることも。
ステップ3:開設許可申請、許可証発行、診療所開設届の提出と実地検査
審査が終わり、疑義がなくなれば開設許可申請が受理され、管理者立会のもと、実地検査が行われて問題がなければ許可証が発行される。
地域によっては実地検査は後日の場合もある。
よくある質問(FAQ)
最後によくある質問と回答をご紹介します。
Q1:非医師が理事に就任することは可能ですか?
可能です。ただし、必ず1院につき1名、常勤の管理医師が必要です。
Q2:開設後に保健所から指摘されることはありますか?
あります。ホームページやSNS等で疑義が生じる記載をしていたり、通報があったり、何かしら疑義があれば突然訪問してくることもあります。
管理者不在、名義貸しなどは厳しく指導、処分されます。
Q3:許可が降りないことはありますか?
法律上の制度ですから、適法に非営利性と、永続性などに問題がなければ許可はおります。が、原則保健所は許可を出したがらないので、受け付けず放置され諦めさせられるというようなことがあります。
相当程度経験豊富な専門家の支援がないと難しい場合もあります。
まとめ:一般社団法人を用いた診療所開設は戦略的準備が鍵
「一般社団法人による診療所開設」は、戦略的に活用すれば柔軟な経営が可能になりますが、原則保健所が嫌がるため難易度は高いです。
だからこそ、事前に医療許認可に精通した行政書士を側においておくことが、成功の分かれ道となります。
医療専門の行政書士へのご相談はこちら
当事務所では、一般社団法人を活用した診療所開設の支援実績が多数ございます。
スキーム設計から保健所対応、設立・開設届のサポートまで一貫して対応いたします。

医療法人の設立・運営面についてサポートします!
医療許認可の専門家として17年。医療許認可1,500件以上の実績。
医療法人化または一般社団法人による診療所開設、
分院開設、医療法務顧問、補助金、助成金支援までサポートしております。
医療法人の専門家にお気軽にご相談ください