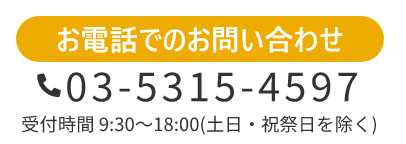医療法人の分院開設、失敗しないための注意点とは?|許認可・行政手続きの落とし穴と対策
分院開設


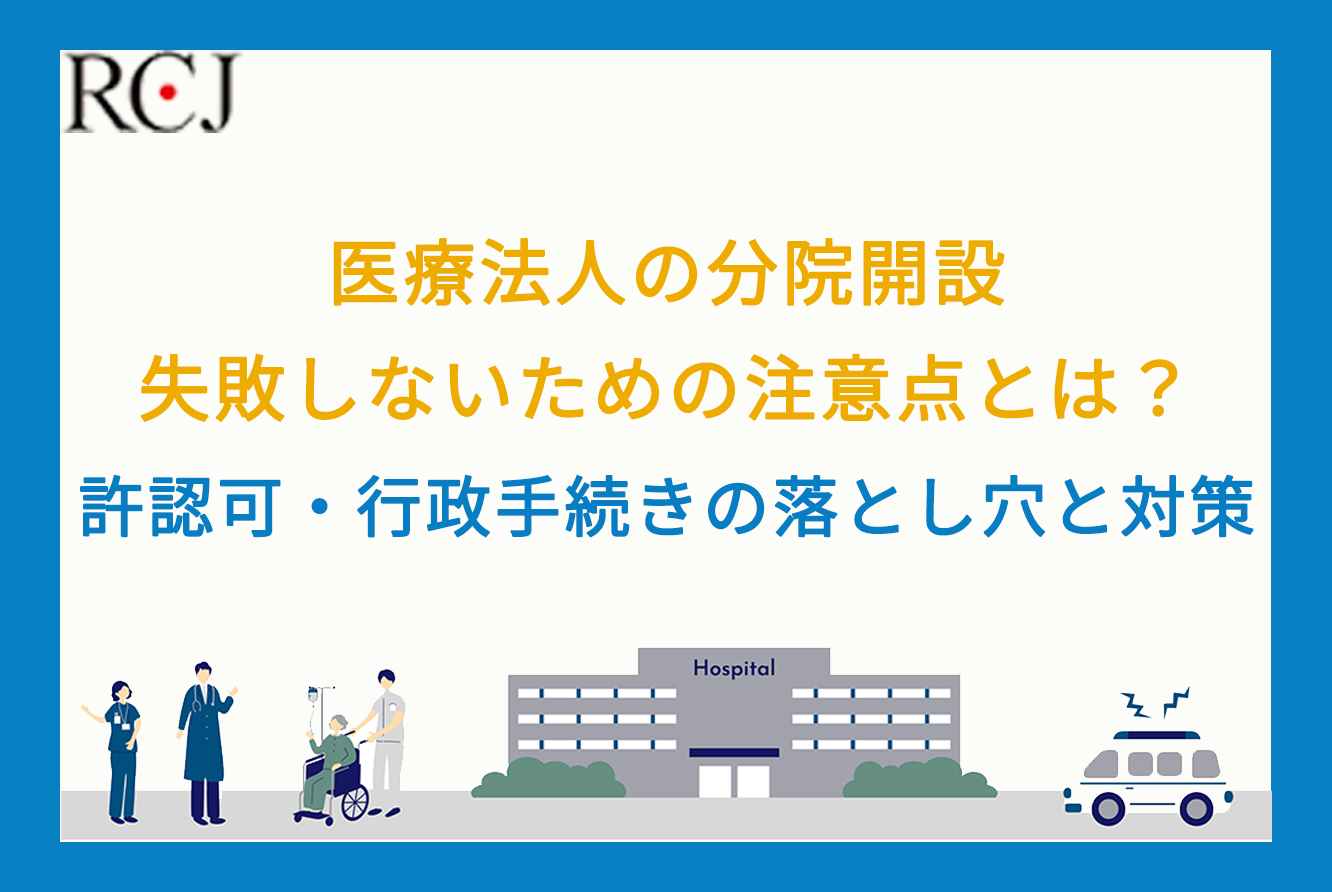
この記事の監修
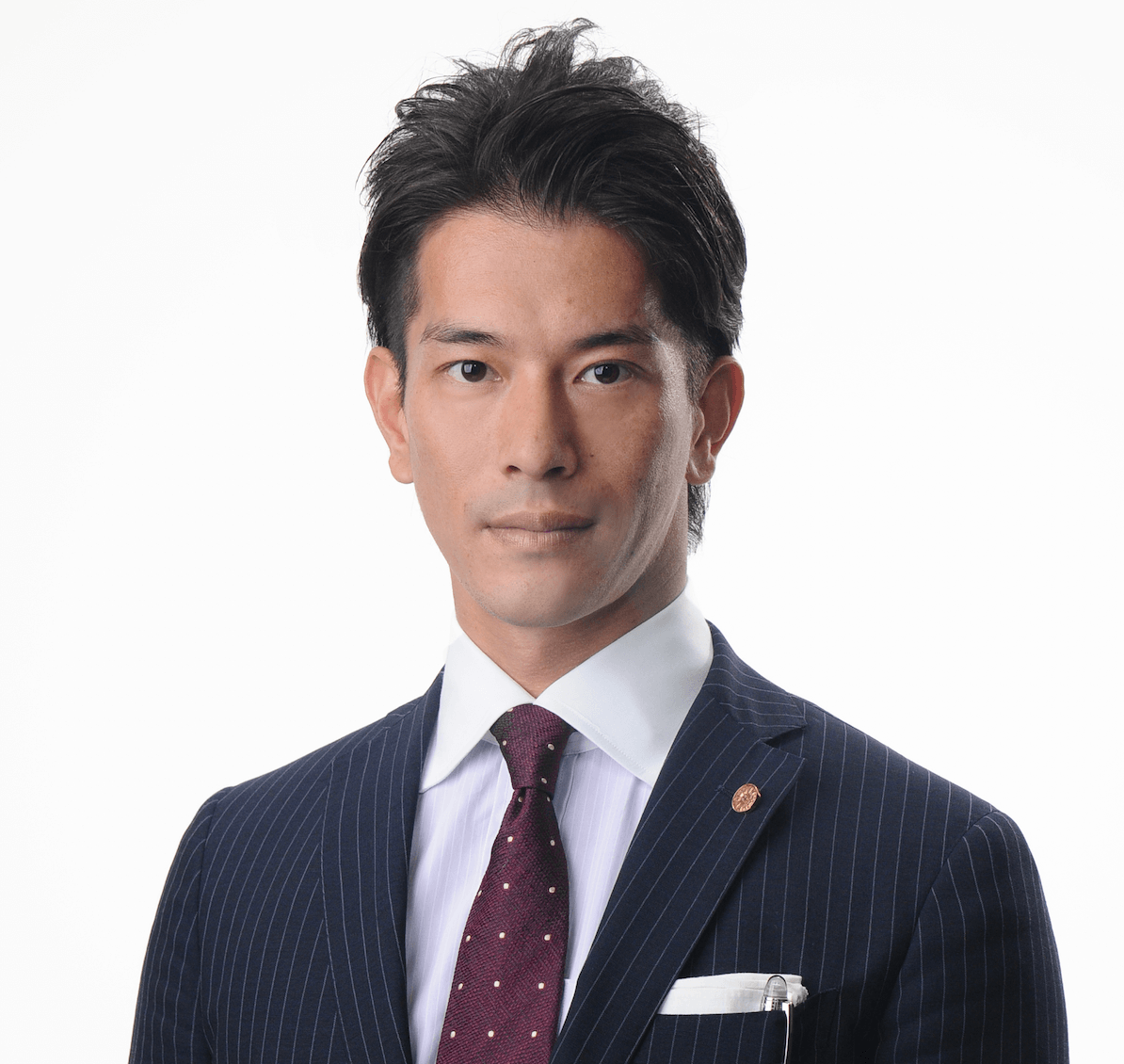
行政書士法人RCJ法務総研 代表 / 行政書士
株式会社リアルコンテンツジャパン(経済産業省認定経営革新等支援機関) 代表取締役
古川 晃
医療許認可の専門家として17年、医療法人設立・分院開設・合併・解散・一般社団法人による診療所開設など医療許認可1500件以上 クリニック様の助成金・補助金・融資などの資金調達100億円以上の支援実績
医療法人として成長し、患者ニーズに応えるために「分院開設」を検討する医業経営者は少なくありません。
特に昨今の競争激化や多様化する診療ニーズの中で、「クリニックの分院展開」は重要な経営戦略のひとつです。
しかし、分院開設は単なる“新規開院”とは違い、医療法や行政手続きに関する複雑な規制が絡みます。
これらを十分に理解せずに進めると、「認可が下りない」「開設が遅れて空家賃や人件費のロスが生じる」「法人運営が不安定になる」など、重大なリスクに直面することがあります。
本記事では、医療法人の分院開設で失敗しないための注意点を、具体的なリスクとその対策も含めて詳しく解説します。
さらに、分院開設のために必須の行政手続きを専門とする「医療許認可専門の行政書士」の存在についてもご紹介します。
1. 医療法人の分院開設とは?
「医療法人」としてクリニックを経営していると、患者数の増加や診療科目の拡大を見据えて、「分院(第二・第三クリニック)を出したい」と考える場面があります。
しかし、分院開設は“個人開業”とは根本的に異なります。
永続性の原則(ヒトモノカネ)
- 新院を開設するにふさわしいだけの資源が備わっているか。
不安定な経営基盤では開設の認可を認めない
非営利性の原則
- 非営利性に反する資金の流れはないか。
理事長への貸付、私的な車両、私的な社宅、ゴルフ会員権や金融商品など、医療に直接関係ない資金流用は不適切とされます。
役員兼務状態の法人との経済的取引は不適切であり、改善を求められることも近年は増えています。
医療法に従い適切な経営を行っていないと、認可を得ることができません。
これらを踏まえずに進めると、開設どころか法人運営に指導が入り、それが改善するまでは認可が得られないというケースが散見されます。
これらは元々NGだったことですが都道府県によって性善説的にお目溢ししてくれていたこともありましたが、年々チェックが厳しくなっています。
特に東京都は他県に比べ圧倒的にチェックが厳しいです。
この認可を考慮せず、物件をとりあえず押さえて工事を始めてしまったが、法人診療所として開設ができないという事例が後を断ちません。
結果、やむを得ず一旦個人開設を行うという方法を取られる方もいますが、この時に医療法人の名義で各種契約をしたり、資金を医療法人から支出してしまったりすることが最悪です。
個人開設の診療所は、当然開設者の診療所であり、医療法人の診療所ではありません。
いかに医療法人の分院にする予定であったとしても、個人の診療所の経費を医療法人が支出してしまうことは不適切です。
さらにもっと最悪なのは、個人開設しながら売り上げを医療法人に計上してしまっているケース。
これは医療法人での開設が認められていないのに売り上げを計上してしまっているわけですから、無許可営業であるということになります。
当然、是正と精算が必要となります。
このようなことがあると認可が長期化します。
そうならないためにも、賃貸物件を契約する前に、必ず医療許認可に詳しい行政書士に相談をし、正しい行政手続きの手順をあらかじめ理解しておきましょう。
2. 分院開設でありがちな失敗とリスク
分院開設でありがちな失敗事例についてご紹介します。
【失敗例1】計画した開設時期に間に合わない
行政手続きの申請不備や、確認事項の漏れで開設が半年以上遅延するケースもあります。
スタッフ採用や広告出稿後に「許可が下りない」事態が発生すれば、大きな損失です。
【失敗例2】認可が下りないままテナント契約・設備投資をしてしまう
内装工事や医療機器の導入を始めた後に、申請が却下されるケースもあります。
これにより、数百万〜数千万円の無駄な支出が発生する可能性があります。
【失敗例3】本院と分院の経営バランスが崩れる
分院にリソースを割きすぎるあまり、本院の診療効率が低下し、法人全体の収益が悪化することもあります。
3. 分院開設における許認可・行政手続きについて
分院開設には、以下のような複数の行政手続きが関わります。
主な手続き項目
- 分院開設のための定款変更認可申請のための事前協議(各都道府県)
→2、3ヶ月程度(不適切なことがなければ)
- 分院開設のための定款変更認可本申請
→受理されてから2週間程度で認可証発行
- 変更登記申請(法務局)
- 診療所開設許可(保健所)
→1ヶ月程度
- 診療所開設届(保健所職員と管理者立ち会いの実地検査)
- 保険医療機関指定(保険診療がある場合、厚生局)
- 施設基準・公費医療等の届出
これらの手続きは、都道府県や自治体によって細かいルールや審査基準が異なる場合があります。
また、申請書類だけで数十ページに及ぶこともあり、通常業務と並行して進めるのは現実的に困難です。
診療を開始したい日からできれば6ヶ月くらい前には都道府県や行政書士と事前協議をして準備をするのが望ましく、2、3ヶ月前ですとかなりタイトなスケジュールとなります。
もし、不適切な改善事項などがなければ間に合いますが、何かでつまづくと遅延が生じます。
4. 専門家(行政書士)を味方につける重要性
医療法人の手続きに精通した行政書士は、分院開設における「手続きの道案内人」とも言えます。
行政書士ができること
- 事前調査(過去の行政手続に漏れがないかなどのチェック。漏れがあれば先に完了させなくては認可に進めない)
- 医療法に基づく分院認可申請の代理
- 各都道府県や保健所との折衝
- 定款変更や法人手続きの代行
- 必要書類の作成・提出・進捗管理
- 開設スケジュールの最適化
失敗の多くは“見落とし”や“誤認”から始まります。
医療法人の法務に精通した行政書士と連携することで、手続きの正確性・スピード・安全性が大きく向上します。
行政書士と言っても、全員が医療許認可に詳しいわけではありません。
むしろ、医療許認可は専門性が高く、経験豊かである行政書士は少数です。
5. 成功するための分院開設ステップ
Step1:市場調査と戦略立案
- 分院の診療科目、ターゲット患者層の明確化
- 商圏分析、競合状況の把握
Step2:事業計画と資金計画の策定
- 初期投資額の明確化
- キャッシュフローと法人全体の収益予測
Step3:行政手続き・許認可対応(行政書士と連携)
- 開設認可・各種届出を専門家がサポート
- 法人の整合性を保ちながら申請
Step4:スタッフ採用・設備導入・ブランディング
- 人材確保と教育体制
- 医療機器や電子カルテの選定
- Web集客・内覧会の実施
Step5:開設後のPDCA体制構築
- 患者数・稼働率・口コミ評価の分析
- 必要に応じて法人運営の見直し
6. まとめ|失敗しないために「今」できること
医療法人の分院開設は、「ただの分院」ではなく、「法人経営の第二ステージ」への突入です。
しかし、そこで重大な行政トラブルや損失を生まないためには、「法的根拠に基づいた設計と実行」が必須です。
今まさに分院を検討している医療法人の経営者様へ。
「どこから手をつければいいのか不安」「申請の流れを一度整理したい」とお考えでしたら、行政手続きのプロである行政書士を味方につけることをお勧めします。
✅【無料相談受付中】医療法人の分院開設サポートなら
医療法務に精通した行政書士が、初回無料でご相談を承ります。

医療法人の設立・運営面についてサポートします!
医療許認可の専門家として17年。医療許認可1,500件以上の実績。
医療法人化または一般社団法人による診療所開設、
分院開設、医療法務顧問、補助金、助成金支援までサポートしております。
医療法人の専門家にお気軽にご相談ください